使い古した参考書を睨みつけながら、葉子はてくてくと通学路を歩いていた。
吐く息が、白く染まる冬。
大学受験、真っ只中――
遊んでいるヒマもなく、
好きな芸能人のライブに行く余裕もなく、
今はややこしい数式を必死に頭に叩き込んで、勉学に励む毎日だ。
(めざせ、志望大学! 一発合格!)
などと気合を入れ、開いたページを食い入るように凝視した。
その時――
「葉子、おはよ」
「!」
ふいに真正面から声を掛けられ、下を向いていた彼女は、はっと我に返った。
驚いて顔を上げると、目の前ににっこりと笑顔を浮かべた男の子が立っている。
「――貴之」
「お前、朝っぱらから勉強してんのか。頑張ってるなぁ」
教科書の背表紙をつん、と突付いてきた貴之を見上げ、葉子はむっと口を尖らせた。
「……だって、ゼッタイ合格したいんだもの!」
「だよな。今は彼氏のオレより、教科書の方を愛してるって感じ」
「――」
「はい、これ。差し入れ」
そう言って差し出された小さな袋を受け取り、葉子は嬉しそうに頬を緩めた。
「わぁい、プチシュー?!」
「そ。オレの手作り」
「美味しそう〜!」
中身を覗くと、小さなシュークリームが5つ。
ちょこんと袋の底におさまっていた。
貴之の家は、曽祖父の代から続く老舗の洋菓子屋さんだ。
ガトーだのフランボワーズだのロッシェだの、そんな洒落たお菓子はないけれど――、彼の
お店で作る素朴なイチゴ・ショートやクッキーは、この辺りで1番おいしい商品だと自慢できる。
「いいなぁ、貴之は。受験しないでお店の跡を継ぐんでしょ。勉強しないで良いなんて、羨ましい」
「バッカ。これでも苦労してるっての! 未来のケーキ職人は、修行にいそしむ毎日なのだ」
ふふん、と鼻を鳴らす恋人を見上げ、葉子はなおも「……いいなぁ」と呟いた。
毎日毎朝――
受験勉強に追われる葉子のために、彼はいつもお菓子を作ってくれる。
その気持ちがとても嬉しい。
「おいしいけど、太りそうなのよね」
葉子が困った顔で歓喜の悲鳴を上げると、貴之が首を振った。
「これくらい平気だよ、甘さひかえめだし」
「そっかなぁ」
「多少の糖分は、脳を活性化するし、ストレス解消にもなる。大事な時期なのに、苛々して勉
強できなかったら大変だろ」
「……うん。……ありがと」
葉子がお礼を言うと、彼は袋に手を伸ばし、プチシューをつまんで彼女の口に放り込んだ。
「おいしい〜!」
「だろ」
得意げな顔で、貴之が笑う。
受験勉強は、ノイローゼになりそうなぐらい大変だけど、彼の笑顔を見ていると頑張れる。
(春までの辛抱だよね!)
そう自分に言い聞かせ、葉子はもうひとつ、プチシューをぱくりと口に入れた。
+++++
悪夢の判決が下されたのは、数日後のことだ。
――C判定!
(……うそっ、あんなに勉強したのに、どうして……!)
先日の模試の結果を手にして、愕然とした。
ガケっぷちに立たされた気分で、落胆にくれる。
――どうしよう……っ。
こんなんじゃ、志望校に合格できない。
今よりもっと頑張らなきゃ、絶対に落ちる!
そんな恐怖が、体中を支配する。
(もっと勉強しなきゃ、努力しなきゃ……っ)
がらがらと足元が崩れるような思いが、体の奥底から染み出てくるのを堰き止めることすら
出来なかった。
「葉子? どした?」
小首を傾けて、貴之が覗き込んできた。
判定表をぐしゃりと手中で丸め、蒼白した表情で顔を上げる。
「な、なんでもないっ」
「……ていう表情じゃないけど、なに、気になるだろ」
「――っ」
不安げに瞳を陰らせた貴之から視線をそらし、葉子は苦渋の表情を露にした。
「……貴之」
「ん?」
「……しばらく会うの、やめない?」
「――」
彼は、なにも言わなかった。
葉子の言葉を予想してたかのように、無言になり、きゅっと唇を引き結ぶ。
「……いつまで?」
「受験が終わるまでかな。そろそろ追い込みだもの。私も本気ださないと」
「あぁ、……うん」
迷いとも肯定ともとれる曖昧な返事を返し、彼は口をつぐんでしまった。
とたんに、重苦しい空気がたちこめる。
「あの、さ。……葉子、ちょっと気負いすぎじゃない?」
「!」
「前から見てて思ってたんだけど――なんか思い詰めすぎというか……合格しなきゃ人生終
わり!みたいな雰囲気が伝わってきて、オレ、すごく心配になる」
「し、しょうがないじゃないっ。浪人なんてイヤだもの、受験ってそういうものでしょ」
「……そうかもしれないけど、もっとこう、リラックスするとかさ」
「っ!」
その言葉にかっとして、葉子は怒りに頬を紅潮させた。
挑むような視線を投げかけ、貴之を睨みつける。
「な、なによ。気休めなこと言わないでよ。貴之になにが分かるの?!」
「なに、って……」
驚いた貴之が、双眸を開いた。
食い入るように見つめられ、その表情を見たとたん、彼女の中にやりきれなさが溢れた。
「オレは、……葉子がムリするのが気になって」
「やめてよ、親の跡を継いで楽しよう、なんて思ってる人に、何が出来るのっ。私の苦労なん
て知らないくせにっ」
次から次へと、ヒドイ言葉が溢れてくる。
口にするたびに彼を傷つけると分かっているのに、止まらない。
「た、貴之には、受験生の辛さは、きっと理解できないと思う……っ」
「!」
言ったとたん、涙がこぼれた。
「……葉…」
憐 憫の色を含んだ顔で見下ろされ、自分の方へと伸ばされた手を、ぱしりと払った。
凍りついたような貴之の顔を、葉子は見ることすら出来なかった――
翌朝。
学校に行くと、彼女の机の中に、小さなお菓子の袋が入っていた。
もちろん、入れたのは貴之だ――
数枚のクッキーと、英単語の書かれたメモ用紙。彼の気遣いが目に見えるようで、書きなぐ
ったような歪んだ文字を前にして、
……泣けてきた。
(お互いに、ほんの少し、我慢すればいいんだよね)
デートなら、合格してからでもできるんだから。
映画も、遊びも、全部後回しにして、
いつか来る春を楽しみにしながら、
今はただ、ひたすらやるべきことをやろう、と心に決め、葉子はやる気を奮い立たせて、ひ
とり参考書を睨みつけた。
+++++
放課後。
スクールキーパーから鍵を預かった貴之は、たった1人で家庭科室にいた。
調理台に、ずらりと並んだキッチン道具の山。
卵黄、砂糖。つぶした果実にミルクを混ぜて、ひたすらシェイクシェイク。
「……うわ。あぁ〜」
生クリームの入ったボールを見下ろし、お菓子作りに励んでいた彼は、とたんに落胆の息を
落とした。
受験勉強を頑張る葉子のために、何とか力になりたいと思うのに、何度やってもうまくいか
ない。
しぼんだメレンゲの山に眉をひそめ、流しにがしゃん、とセラミックの器を放り込んだ。
その直後――
「あれ、貴之くん?」
「!」
振り向くと、同級の女子が、ドアの隙間からひょこりと顔を覗かせていた。
「わぁ、いい匂い。お菓子作ってんの?」
「うん」
「彼女へのプレゼント? すごいなぁ」
「……そんなことないよ。全然うまく出来ないし」
「えー、でも美味しそうよ?」
少しもらっていい? と断って、彼女が冷めたスポンジの欠片を口に入れた。
とたんに、満面の笑みがこぼれる――
「美味〜!」
「……お前、うまそうに食うな」
「そぉ? だってこれ、ホントに美味しいわよ。ね、作り方教えてよ」
「――」
そんな風に笑顔で頼まれ、少し落ち込んでいた貴之は、失いかけていた自信をわずかばかり
取り戻した。
「ねぇねぇ、知ってる? 貴之くんが放課後、お菓子の作り方を教えてくれるんだって!」
「わぁ、見たい見たい」
「行ってみようよ!」
そんな噂が、瞬く間に学校中に広まった。
参考書に視線を落としながら、葉子は気が気じゃない。
心の中で、こっそりと
(……就職組は、お気楽よね)
などと呟きながら、
「今は勉強が一番なんだから、ほかのことは気にしないっ」
と、自分に言い聞かせる。
――が。
ざわりとよぎる不安が、胸から消えない。
(だ、大丈夫だよね……貴之……)
開かれた教科書の文字を追いながら、彼女の視線は、まったく別のところに飛んでいってし
まっていた。
受験勉強も手につかず、気もそぞろ。
そんな葉子の思いとは裏腹に、貴之は毎日、彼女のためにお菓子を届けてくれる。
毎朝、机の中にはいっている小さな袋。
そこには、葉子の勉強に役立てようと、いつも英単語つきのメモが添付されている。が、今
はそれすらも鬱陶しく感じてしまう――自分に嫌気がさす。
「……」
複雑な表情で眉根をよせ、お菓子の入ったラッピング袋を握りしめていると、
「葉子、おはよ」
「!」
教室の中に貴之が入ってきた。
「……おはよう」
遠慮ぎみに挨拶をすると、彼は嬉しそうに彼女が手にした袋を指差した。
「それ、新作なんだよ。葉子に1番に食べて欲しくてさ。今度、感想聞かせてよ。リクエスト
あれば、なんでも作るからさっ」
満面の笑みを浮かべ、満面の笑みで近づいてくる。
そんな彼の表情を目の当たりにし、直後、胸にずきんと痛みが走った。
「……いいよ」
思わず、そう口走る。
貴之が不思議そうな顔で小首を傾げた。
「え」
「いらない、って言ったの。……もうこんなことしないで……受験までほっといてって言った
でしょ」
「え、でもさ」
「このお菓子だって、どうせ女の子たちと一緒に作ったんでしょ! そんなのを私に食べさせ
るなんて、無神経すぎよ!」
「――」
呆気に取られたまま、貴之が立ち竦む。
どう答えてよいのか、考えあぐねているような彼を睨みつけ、葉子は居たたまれなくなって、
きびすを返した。
「葉子?!」
ざわざわと、クラスメートたちが騒ぎ出す。そんな中で、貴之は身動きすら出来なかった。
「ちょっと待ちなさいよ」
葉子が、1人の女の子に呼び止められたのは、ちょうど廊下を曲がった時だ。
いきなり肩をつかまれ、ぎょっとして振り向くと、目の前に同級生の女子が立っていた。
小さく嘆息し、葉子に挑むような視線を投げかけてくる。
「……なによ」
「今の言い方、ちょっとヒドクない? 受験でイライラしてんのも分かるけどさ、貴之くんの
気持ちも考えてあげたらどうなのよ」
「――そんなの、あなたに言われる筋合いじゃないわ」
「意地っ張り」
「!」
「要するにヤキモチでしょ。自分から突き放しておいて、彼がほかの女の子と仲良くしたと
たん、気になり始めたんでしょ」
「……っ」
図星をつかれて、葉子はひるんだ表情を見せた。
にやりと不敵な笑みを浮かべて、彼女が呆れたように葉子を見据えてくる。
「彼はあなたに夢中なんだから――、誰がアタックしたってビクともしないんだから、もう少
し彼を信じてあげたら?」
「――!」
まったくもう、面倒くさいったら……。
そうボヤいた彼女が肩をすくめるのを、葉子は呆気に取られて見つめていた。
「ま、いいけどさ。貴之くんにはちゃんと謝っておきなさいよ。今のは絶対あなたの方が悪い
んだからっ」
そう言って、くるりと立ち去っていこうとするのを、葉子は慌てて呼び止めた。
「あ、あの……?」
「そうだ、忘れてた。もうひとつ!」
葉子の言葉を聞かず、肩越しに振り返った彼女は、指を突き立てて葉子の方に示した。
「勘違いしてるみたいだから言っとくけど、彼があなたに届けてたお菓子って、アレ、貴之く
んがひとりで作ったのよ」
「え!」
「間違っても、あたし達と作ったり、お店のを持参してるわけじゃないから――あなただけに
特別に作ってたんだってこと、覚えておいてね」
「――」
「じゃあね。せいぜいお勉強がんばりなさいよ」
ぽかんと突っ立ったままの葉子を置き去りにし、彼女が立ち去っていく。
「あのっ……ありがと! 教えてくれて、ありがと!」
その声は、彼女の耳には届かなかったかもしれない。
歩を緩めもせず、廊下の向こうに立ち去っていくクラスメートの姿を追いながら、葉子は慌
てて近くの階段を駆け下りていた。
+++++
貴之の姿を探す――
本鈴のチャイムは、とっくに鳴っていた。だが、そんなことを気にする余裕もなく、ダッシ
ュで校舎を飛び出していた。
さわさわと、風が鳴る。
冬の冷たい空気にさらされながら、葉子はコートも着ずに中庭を駈けていた。
そして――
「貴之……!」
ようやく彼を見つけた時。
貴之は、校舎の端っこに寝転んで、昼寝を決めこんでいた。
つんと立った芝生の上に仰向けになり、葉子の呼び声にすら反応せず、熟睡している。
その胸元には、読みかけのお菓子の本が広がっていて、風が吹くたびにぱらぱらとページが
めくれていた。
「……貴之……っ」
彼の近くにしゃがみ込み、そっと表情を覗き込むと、ようやく彼は、寝ぼけた顔で上体を起
こした。
「……あれ、葉子?! なにやってんの、お前。勉強は?!」
「……そっちこそ何してるのよ。授業、始まってるわよ」
「オレは――だって、受験組じゃないからさ」
戸惑いぎみに顔を上げ、貴之は胸元に落ちた本を手に取った。
ぎこちない仕草で本をまるめ、投げるように芝生に置かれたそれを見つめ、葉子は「ごめ
んね……」と呟いた。
「へ?」
「ごめんね、貴之。……あたし、自分のことばっかりで……自分だけが一生懸命で、貴之はお
気楽だって思って……っ、ずっと妬んでた。――本当は、貴之が1番あたしのこと思っててく
れたのに、頑張ってるのはあたしだけだ、って勘違いして――っ」
「よ、葉子……?」
俯いたまま、あふれ出る涙をぬぐいもせず俯く。と、膝元にぽたぽたと雫が落ちた。
あたしって、すごい、バカ……!
今頃こんな大切なことに気付くなんて。
貴之がいなきゃ、頑張れない――
1人で勉強しても、応援してくれる人がいなきゃ、力が出ない。
いつか春になって、合格発表を見に行くときに、貴之にそばにいて欲しい。
その笑顔で、あたしと共に喜んで欲しい。
あたし達は、2人で受験に挑んでいるのだと――
そう気付くのに、ずいぶん時間が掛かってしまった。
「……貴之、……好き」
「! は、……あ?!」
ぎょっとした顔で、貴之がかぁっと赤面した。
なに言ってんの、お前――っ、と照れた仕草で、戸惑っている。
「今さらだけど、すごく、好き」
「――う、うん。……オレ、も」
独り言にも似た囁きが、2人の間に落ちた。
「春まで、一緒に頑張ろうぜ」
そう言って、いつも励ましてくれる。
彼の優しさに、ずっと甘えていたのだと、改めて気付かされた。
「――うん……」
‘一緒に’、と貴之は言う。
その言葉を、忘れないでおこう。
ちゃんと胸に刻んでおこう――
こくりと頷き、彼女は顔を上げて、にこりと笑った。
「なぁ、オレいいこと思いついたんだ」
「なに?」
「これこれ、新作お菓子! マグロの目玉、頭が良くなるDNA入りクッキー。どぉ?」
「――すごく……ダイエットに良さそう……」
「なにそれ、腹こわすって意味?」
憮然とした表情で、お菓子のレシピ本を握り締める貴之を見つめ、葉子はくすくすと肩を揺
らした。
――春が、近い。
2人が心の底から笑顔で抱き合うのも、きっと、もうすぐ……。
−終−
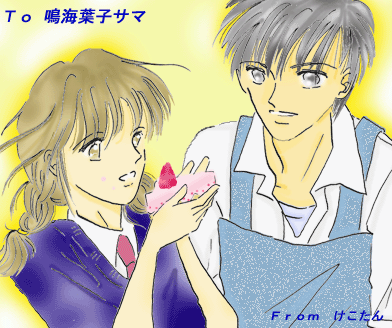
**********************************************
けこたんサマ、素敵な作品ありがとうございます!!
しかも、主人公の女の子にわたしの名前を使っていただけて、
感激のあまり涙がこぼれ落ちます。
葉子ちゃん、やっぱり受験って大変ですよね。テンパッテしまう
気持ち、よーく分かります。
中盤、いったい二人はどうなっちゃうのーっ!と絶叫してましたが
ハッピーエンドになって、本当によかった。
わたしも貴之くんのような、広くて深い愛を注いでくれるような
そんな素敵な彼が欲しくなってしまいました。
けこたんサマ、これからも仲良くしていただけるとありがたいです。
そして、なんとけこたんサマが続編を書いて下さいました。→こちら